「魔導具師ダリヤはうつむかない」の二次小説です。
コミカライズから読み始めて、面白くて即日ライトノベル既刊分も全冊読破、先が気になって「小説家になろう」で先読み。更新を首を長くして待つ日々です。
本日発売した8巻は0時になると同時に購入、夜更かしして読破。泣ける素敵な展開でしたが恋愛面はモヤモヤだったので糖分を自給自足することにしました。
そして出来上がったのが「恋人同士になった二人を囲む愉快なひとたち」の話に。シュガーレスな内容になりました。
訓練場の一部の修繕が必要とのことで、予定より数時間早く繰り上げて終わった訓練。
いつもより余力が残る隊員たちはこれで兵舎に戻るのも味気ないと、食事だの花街だのこれからの予定に花を咲かせていた。
そんな会話を聞きながらヴォルフはその金色の目に真剣な光を灯し、鈍く紅く光る己の剣を丁寧に拭きとり鞘にしまった。
「ヴォルフ、せっかくだから黒鍋にでも行かないか?」
同期のドリノの言葉にヴォルフは一瞬悩んだ様子を見せたが、腰元でカチャリと剣が鳴ったのをきっかけに笑顔で首を横に振る。
「今日はパス。商業ギルドでの仕事が夕方までだったから迎えに行こうと思うんだ」
塔に直接押し掛けるわけではないし、恋人になったのだから先触れなしのサプライズも許されるだろう。照れ臭そうにそう言う美丈夫に、ドリノは軽く見開いた目を数回瞬いたあとニヤリとしか形容できない表情をして
「なに?」
「いや~自覚するまで長かったけれど、始まっちゃえば早いなと思って」
「もともと『恋人同士じゃないことがおかしい』かったからな」
どの次元から見ても両思いだろうとしか言えない二人だったが、ヴォルフの自己評価の低さと、なによりダリヤの鈍感さが悪い方に作用して恋人になるまで時間がかかった。
『ダリヤと恋人になりました』
愛する弟からそう報告を受けた兄のスカルファロット侯爵は、錆色の髪の親友と年代物のワインで盛大に祝杯を挙げた翌日、周囲にクギを大量に刺してまわった。
私の大切な義妹に粉をかける愚か者がいないとは限らないからね、とキレイな笑顔。さらには、父親である元侯爵も、クギを刺してまわる息子に「自分の分もよろしく」とクギを提供したという。そのことにヴォルフは驚き、少しだけ胸がくすぐったくて笑ってしまった。
ちなみに、そのうち一本のクギがしっかりと刺されたゾーラ家。
当主であるオズヴァルドは、そのクギの後ろに見える氷塊にいささか肝が冷えたと妻たちに漏らしたとか。
「会長……、大丈夫ですか?」
心配を音ににじませたイヴァーノの声に、しばらく同じ羊皮紙を眺めていたダリヤはハッとして顔を上げた。
その顔色はいささか青く、もしや病気かと焦ったイヴァーノの脳に銀衿の神官がポンッと浮かぶ。銀衿という高い地位にありながら、食い意地のおかげで商会とは懇意の仲となっている。
「大丈夫です……少し気分が優れなくて」
ダリヤの『大丈夫』ほど”大丈夫じゃないこと”は無い、という認識はその場にいる数少ない商会員全員の共通認識。
「顔が少し火照っているようですけれど、風邪じゃないですか?」
「そうかもしれませんね。 会長、今日は仕事がない……わけではないですが、どうにでもなるので、この後は塔でゆっくりとなさっては?」
『仕事がない』と言うには少し、いや、かなりの無理があった。権利書などの書類は山と積まれており、そんな机を見ながらマルチェラはダリヤに提案する。
「本当に大丈夫です。 本当に、その…病気ではないので………すみませんっ!」
普段は穏やかで所作も落ち着いているダリヤが急に椅子を大きく鳴らし、口元を手で覆って部屋を出て行くのを男たちは茫然と見送ったが、
「「「 まさか 」」」
イヴァーノとマルチェラは妻と二人の子持ち、メーナは独身ではあるものの孤児院育ちで自由恋愛派なため女性のことには詳しい。
そんな男三人は同じ答えに行きつき、同時に脳内に金目の黒犬を思い浮かべた。
「会長、今までは香水なんてつけなかったのに最近はレモンのようなニオイをつけてますよね」
「レモンと言えば、この前ダリヤちゃんが大量のレモンを買ってたってイルマ言ってた」
「そういえば、最近は腹部が緩やかな服を着ていることが多いような」
『そうではないか』と疑い出すと、答え合わせをしたくなるもの。男たちは情報を照らし合わせて自分たちの予測を確信に近づけていく。
「お二人が『友人』と主張しているときは焦れったく思いましたが、進展すると一気に進むものですね。まあ、休みのたびに塔で逢っていれば不思議ではありませんが」
「娘を持つ親としては『順番を』と言いたいところですが、グイード様は”勢い”とも言っていましたし、あちらの家とも懇意ですから順番など些末なことでしょうね」
「そのときになったらドレスを作るってデザイン貯めていたルチアちゃんは発狂するかもしれないがな」
「しかし…この先、ヴォルフ様の過保護が加速しそうで怖いです」
「元々過保護な気はあったが、恋仲になって枷が取れて遠慮が無くなったよな」
噂をすると、というのは実によくあることで
knock knock
覚えのあるリズムで叩かれた扉を横目に、男たちはお互いの顔を見合わせ
「会長が言っていないので黙っていましょう」
「そうだな、これはダリヤちゃんから言わないとな」
「顔に出さないのが大変です」
三者三様の手段で顔を作ると、それを確認したイヴァーノが「どうぞ」と黒髪の男を招き入れた。
このとき三人は気づかなかった。
ヴォルフが来る少し前、完全に閉まり切っていなかった商会の扉の前から一人の男が慌てて走り去っていったことを。
「ダリヤ先生がご懐妊? 相手は……まあ、確認するまでもないが、その噂はどこから?」
「商業ギルドだ。うちの騎士に確認したところ、ダリヤ先生は気分が優れないからと早めに塔に帰宅、偶然ギルドに来たヴォルフ自身が送っていったらしい」
「で、ヴォルフ自身はそのまま泊まっていった、と。 まあ、このところの生活を思えば先生がそうなったのも分かるが」
「これからの激務を思えば順番を守って欲しかったとは思うが。まあ、急いで式の準備だね。ドレスの方はルチア嬢がどうにかしてくれるだろう」
「スカルファロット家から工房に仮眠ランタンをいくつか贈るべきだな」
「ふふふ、とうとう私も『叔父様』か。私としては女の子をすすめたいが、ヴォルフ似の娘となると苦労が多そうだね」
「激しく同意する。 まあ、ダリヤ先生似の娘でもグローリア嬢と同じ苦労をするだろうな」
「ヴォルフは高い壁となりそうだね。しかし男の子でも……なんだろうね。今まで以上に我々が大変な目に合うイメージしかわかないね」
「子がある程度成長するまでに効果の高い胃薬が開発されると良いのだが」
グイードとヨナスの頭に、同じ胃薬を愛用する面々の顔が浮かぶ。
「すごいことになりそうだな」
「名書きは誰がするのだろう? 私も名乗りを上げたいが未だ弱輩の身だし、父もいるから先ず無理だろう」
「立候補する気だったことが驚きだ。 まあ、ダリヤ先生は御親戚とも縁がないと言っていたから、”スカルファロット家の誰か”になるのが道理だが、無理を通そうとする人達が多過ぎる」
「そうだね、父には頑張ってもらわないと。強敵は”娘扱い”しているジルド様と、”孫娘扱い”をしているお前のお祖父様あたりかな」
「お祖母様が怖いな。『赤子の父親の師匠の祖父』でも、女性貴族をまとめあげて強引に”身内”にしてしまいそうだ」
「ヨナスがさっさと子を作ってくれれば良いのに」
「俺を人身御供にするな」
「つれないね。東の国では『龍に願い事をすれば叶う』って言われているのに」
「それなら美しい女性か七つの宝珠を供えてくれ」
「ヴォルフ~、隊長が部屋にきてくれって言ってたぞ。すごく真剣な顔だったが、お前なにかしたの?」
隊の仲間であり親友のドリノの言葉にヴォルフは礼を言いながら首を傾げる。
思い返してもここ数週間は「便利そう」で新しい魔導具を作り出していないし、五本指靴下も定期的に納品できていると聞いている。
何の用事だろう、と考えたもののグラートを待たせてはいけないと身支度を済ませて隊長室に急いだ。
隊長室に行き、従者に入室の許可を取ってもらう。特に注意を受ける心あたりがなかったため「失礼します」と気楽に入室しが、その気楽さが室内のにいた人物で一気に吹き飛ぶ。
ここにグラートがいるのは分かっていたが、ジルドが来ているのは予想外だったからだ。
ジルドに対しては元々苦手意識があり、ダリヤのお披露目会の借りが恋仲になって重みを増した。
つまり、ヴォルフにとっては『頭が上げてはならない人』のひとりなのだ。
しかも今回は、やけに『いたたまれなさ』をビシバシと感じる。
「さて、来てもらったのは今後のことについてなのだが、まあ気楽にしてくれ。そうだ、折角だから年代物の白ワインがあるから開けよう」
無理です、と声高に訴えたいのをグッと我慢して勧められたソファに座る。
先にヴォルフの前のソファに座っていたジルドの威圧が痛い。
ついでに、まだ朝陽が昇ってから数時間、午前の鍛錬が終わったとはいえ酒を飲みかわす時間ではない。
「ヴォルフ、我々に報告することはないか?」
「報告、ですか?……あ、もしかして暑くて眠れないといった俺にダリヤが作ってくれた冷感敷マットのことでしょうか? それか、夏になると暑さで倒れる隊員が多いって相談したときにくれた塩飴のことですか?」
「マットや飴については後で聞かせて欲しいが、それではない。 本当に分からないのか?」
「はい」
嘘をついているとも、誤魔化しているとも思えない曇りないヴォルフの眼。
顔を見合わせたグラートとジルドは、長年の友人関係で築いたアイコンタクトで意見を交換し、
「ダリヤ先生がご懐妊だと、噂が流れている」
「ご、かい…にん? ダリヤ、が?」
ヴォルフの驚いた顔に、『もしや、この男ではないのか!?』という焦りが二人の頭に飛び込む。
(どういうことだ!? ロセッティに他にも男がいたという話は聞かないからこの男だと)
(私もそう思っていた。当然だろう?もともと独占欲が強い貴族的な男だぞ!? そう易々と他の男を近づけるとは思わないだろう!)
(じゃあ、なんだこの反応は?)
(……恋人に子どもができてビックリ?)
(高等学院の生徒じゃあるまいし………ん?そうなのかもしれんな)
初等教育並みの『友人』期間を思い出したジルドは一人勝手に納得していたが、ヴォルフとダリヤの『上司』にあたるグラードはただおろおろとしていた。
ヴォルフの兄侯爵は弟を溺愛している。その弟の恋人への横恋慕、顔も知らぬ間男が血しぶきに包まれるシーンが簡単に想像できてしまった。
「あの……その…妊娠中に『生理』って……くるのです、か?」
「ん?」
「いえ、俺が学院で習った感じだと…妊娠したら生理は来ないものだと……だから、今回も残念だったなって思ったのです、が」
「いや…お前の認識であっているぞ? ということは、妊娠じゃ、ない?」
「はい……彼女はいま、その生理中で……吐き気に貧血と、言われてみれば妊娠中の症状と似ていますね」
「先生がその……それで体調が悪かったから、急ぎ外出許可を取って塔に泊まった、ということか?」
「そうです」
恋人とはいえ、人の事情を勝手に話してしまったことに気まずさを感じながらも説明したヴォルフの目の前、侯爵家の当主たちは大きなため息をついた。貴族の矜持でずるりと姿勢を崩すことはなかったが。
「妊娠中に生理が来ることはない」
「そう、ですよね」
「我々の勘違いだったようだな……まあ、この手の噂は”半信半疑”というところだから数か月もすれば間違いだったと笑い話となるだろう。ただ、ロセッティにはこの噂のことを伝え、あの元気な服飾師を止めるだけはしておいた方が良いな」
「数か月……結構長いですね」
「まあ、お前がロセッティに重いもの持たせて大通りを歩かせれば直ぐに否定もできるが、まあ、難しいだろうな」
「それはちょっと……」
「あとは真実を噂に近づける方法もあるが……やめてけ。イヴァーノ辺りが過労死しそうだ」
「そう、ですね」
苦笑しつつも少し目を泳がすヴォルフに、ふとジルドがさっきの会話を思い出した。
目の前の男は『今回も残念だった』とか言わなかったか?、と。
「ヴォルフレート、追い込みは魔物だけにしておけ」
「何のことでしょう」
ヴォルフの顔に整った笑みが浮かび、侯爵家当主たちは揃ってため息をついた。


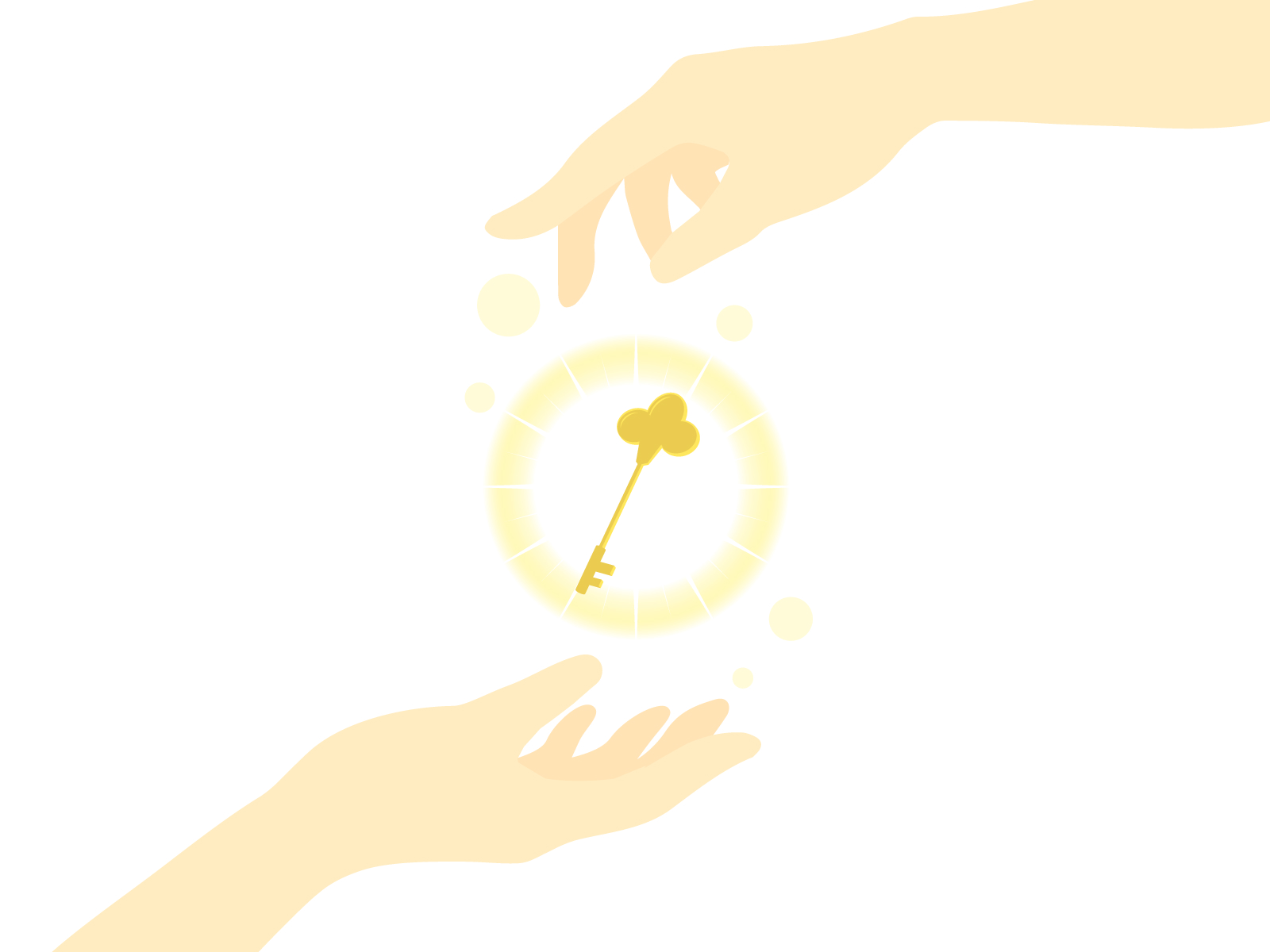
コメント