「魔導具師ダリヤはうつむかない」の二次小説で、ヴォルフとダリヤは恋人同士の設定です。原作の微糖も大好きですが、原作好き過ぎで糖分過多なヴォルダリを自家発電しています。
今回は「小説家になろう」の最新話(#401)を読んだ瞬間に浮かんだ妄想ですが、知らなくても読めるものになっていると思います。
スポンサードリンク
――― 明日から遠征だから、今夜はダリヤを補給させて。
甘い夜に誘うのんびりとした声はいつも熱を孕むが、遠征前日の夜に囁かれる言葉は熱い中にひやりとした『何か』がある。
その『何か』に気づきたくない。
けれど、その自分の体にまわる男の腕の力に、男のその責務に、否応なしに『何か』を知らされる。
”あの日”を境に、ヴォルフは変わったとダリヤは思う。
思えば、魔物討伐隊の者全員が変わったとも思う。
以前は遠征に行くとき、真剣さはあるもののどこかピクニックのような気軽さがあった。
しかし、”あの日”から『もしかしたら』が彼らにも、そして彼らの無事を願う者たちにもつき纏う。
魔物討伐隊に復帰した経験豊かな先輩騎士の後輩ベルニージは「それも成長」と、ひな鳥のような後輩騎士たちの成長を喜びつつ、どこか痛まし気な、複雑そうな表情をしダリヤに向けた。
「ダリヤ」
己の名を呼ぶ男の咎めの混じる声にハッとして目を開ければ、視界を占めるヴォルフの黄金色の瞳が『集中して』と訴える。
しまったと思いつつも胸の底に溜まった澱のような色々を聞かせるわけにもいかなくて、詫びる気持ちと誤魔化しを半分ずつにして、太い首に回した自分の腕に力を込める。
至近距離にある黄金の瞳は甘さを増し、緩くカーブを描く薄い唇が、顎を伝って首筋を吸う。
「ヴォルフ」
今度はダリヤが咎めるように名前を呼ぶと、軽く痛みを感じるほど強く吸われつつあった肌からヴォルフの唇が離れる。
痕が残ったら困ると思ったが、『許して』とばかりに肉厚の舌でベロリと舐められると仕方がないと思ってしまう。
こんな風に二人で甘く過ごす夜はすでに両手では数えられないほど。
謝るような態度をみせつつも、満足気な瞳のヴォルフをみればきつく吸われたそこには痕が残っているのだろう。
初めての夜、ヴォルフはダリヤの体中に赤い花を散らした。
それはもうビッシリと、翌日着る服が遠征夜着一択になるほど盛大に。
【 痕は見えないところに 】
自分では「貴族らしくない」と言っているくせに、ヴォルフは貴族らしい独占欲と執着心を見せる。
約束したと言えないのはヴォルフが納得しなかったからで、今だって嗜めるように名前を呼んでも実にいい笑顔で応えるだけで止めやしない。
これだから顔のいい末っ子は、と甘く、優しく、甘えるように強請って我を通すヴォルフにダリヤは呆れるしかない。
首が隠れる服はあっただろうか。
ダリヤは服道楽ではないが、知名度のある商会の代表として、男爵位を持つ新人貴族として着飾る機会も増えた。
新進気鋭の服飾師である親友ルチアがダリヤのために作る服はどれもダリヤの好みに合わせて露出度控えめであるが、野暮ったくならないように適度に肌は出ている。
おかげでヴォルフと過ごした翌日は服選びに難儀する。
服選びの基本条件と身だしなみを整える時間の大半が男の所有痕を隠すことに費やされている自分に呆れつつも仕方がない。
「俯かない」と決めたのに、誰かに赤い痕を指摘された日には羞恥心で顔を上げられなくなる自信があった。
・・・・・・
唇を離して、白い肌に咲かせた己の花にヴォルフは満足する。
共に目覚める朝を2回繰り返し、3回目の朝に「キスマークをつけないで欲しい」と頼まれたが、そのときは余裕の表情で”聞かなかったこと”にした。
しかし、これについて普段は甘いほど優しいダリヤが決して折れなかった。
しかも最初はキスマークの件だけだったのに、どうしてそうなったのか、頻度や一夜の回数、終いにはむつみ合う時間の見直しを提案されたところで真剣にマズイと感じた。
とにかくキスマークの件を話し合おう。
その他のことは聞かなかったことにしよう。
そう決めて、つけないのは無理だから「他の人には見えないところになら(つけてもいい)」という条件で締結した。
これについてはダリヤの協力、他の人に見えないように首の隠れる服を着てもらうなどの協力が必須なのだが、全力で愛している最中にそんな余裕はないというのがヴォルフの主張だった。
「明日の朝、俺が出る頃には消えているよ」
「遠くまで行くの?」
「王都から2つ目の宿場を過ぎてすぐの森だから、あまり遠くないよ。そこに小鬼の集落ができそうなんだ」
スライム一匹仕留めるのにてんやわんやのダリヤ。
だけど魔物討伐部隊の強さに信をおいているから、「小鬼」と聞いて安心してくれた。
安堵するダリヤの表情に、自分も少しだけ強くなれたのかもしれないと思う。
”少し”なのはダリヤの優しい緑の瞳に不安があるから、そしてその不安はきっと己の瞳にもある。
――― 小鬼だけなのか?
これだけは何とも言えない。
だからダリヤの華奢な体をヴォルフは強く抱きしめ、背中にまわった優しい腕の感触にほっと息を吐く。
「絶対にここに、ダリヤのところに帰ってくるから」
・・・・・・
「ヴォルフの好きなものを作って待っているわ」
「いまから楽しみだ」
そう言いながら近づく顔に、やがて耳をくすぐる熱い吐息に、もう慣れたと油断していた心臓がトクリと跳ねる。
「俺は君の料理を食べずに死ねない」
重要な秘密を語るような口調で言われて、思わず「なにそれ」と笑ってしまった。
しかし料理に向けて蕩けるような、恋焦がれるような熱烈な視線を向けていたヴォルフを思い出すと妙な説得力がある。
ふと思う。
いまヴォルフは自分に対してもあんな黄金色を向けているのか。
「やっと笑ってくれた―――続きをしてもいいかな?」
照れ屋の自分がそんな問いに答えられるとでも?
おそらくヴォルフは答えることを期待していなかったのだろう、ゆっくりと動き始めた熱い体に燻っていた熱を煽られる。
「……ぁ」
胸元の柔らかい肌をキツく吸われ、痛みともいえる感触に思わず声が上がる。
そして、大丈夫と言ったのに、八本脚馬を使えばすぐの距離のはずなのに、自分を忘れさせまいと痕を残そうとするヴォルフに泣きたくなる。
必ず帰ってくるのでしょう?
それなら変な備えなどやめて欲しい。
望みもしないフラグが立ったりしたらどうするのか。
そう言いたいのに、深く強く痕跡を残して欲しいを思う自分の、体の奥にある熱でも誤魔化されない不安を叱る。
「ダリヤ」
甘く煮詰めたシロップのような愛しい声。
心臓がきゅっと絞めつけられ、腹から下腹部にかけて執拗に花を散らすヴォルフの行為を「ヴォルフは腰派だから」と嗜好のせいにした。
・・・・・・
「ヴォルフッ」
強請るような甘さと、切羽詰まった必死さの混じる声。
首にまわった細い腕に力が入る。
腰を強く押しつけると腕の中の最愛がふるりと震え、蕩けた熱に煽られて背を駆けた情を放つ。
熱に浮かされてぼんやりする頭を深呼吸して冷まし、甘い倦怠感を感じながら体を離すと髪から滴った汗がダリヤの白い体の上ではねる。
こんな些細なことも刺激になるのか。
ダリヤの眉間にシワが寄ったしわが愛しくて、体を屈めてそのしわに口づける。
「ダリヤ」
火照った柔らかい体を抱きしめると、絶対に死ねない、死んでたまるかという気持ちになる。
そんな自分の変化がいまでも信じられない。
ダリヤに会うまで魔物討伐部隊の遠征に赴くのは義務感が八割、残りは騎士の誇りめいたもの。
何か守りたいものがあったわけではないけれど、家のために役に立たない自分ができるくことが魔物と戦うことだと考えていた。
ダリヤに出会ってから、遠征に赴く意味が変わった。
森大蛇の干物、大猪の燻しベーコン。
魔物は隊の食材となり、ダリヤの名が刻まれた魔道具で作られた温かな料理を食べながら楽しむ酒の席で友と笑い合う。
まるで初等学院の遠足。
そう思っていた自分を戒めるようにヒュドラと対峙した。
自分を殺す魔物。
初めて感じた、底冷えするような恐怖。
あのとき、帰らなくてはいけない理由があったことをヴォルフはいまも神に感謝している。
そして、その理由がいま自分の腕の中にいることも。
騎士して民を守る気持ちは変わらないけれど、一番守りたい人。
どんなに強い魔物と対峙しても、その背後にある王都にいる彼女を思えば、剣を持つ手の震えも止まり、踏み出す一歩は力強いものになるだろう。
――― もっとすごい魔導具を作る。
もう十分に”すごい魔道具”を作っているのに、これ以上何を作るのだろう。
それが楽しみであり、少しだけ申しわけなくもある。
最愛の父を亡くしたダリヤが近しい者の死、特に死に最も近い自分の死にどれほど恐怖を抱いているか。
そのために自分から死を祓おうと、守ろうとするダリヤのことを、分かっているけれど気づかない振りをしている。
その気持ちに、血のにじむような決意に甘えている自覚はある。
だけど、大切な者を守ることが騎士としての誇りであり、矜持だから。
そして、それをダリヤも分かっている。
だから男の背に縋るよりも、その背を押してくれる。
己の作った魔道具をたくさん荷物に入れさせて、それでも足りぬと”もっとすごい魔道具”を持たせようとする。
もう十分たくさんあるというのに。
携帯用コンロ、防水布、微風布、五本指ソックス。
「これが無い時代に戻れない、戻りたくない」とつい数か月前までの前時代を知る隊員たちはロセッティ商会への感謝を欠かさない。
衣食住の改善は魔物討伐隊員の補充にも役立つ。
隊員数が多ければ訓練のバリエーションが増え、魔物を効率的に倒せるようになると心身の負担が減る。
本人は武具や防具に詳しくないと言っているが、興味本位で生み出された新素材や魔導具は十分強力な武器だ。
ダリヤ本人は大したことないと言っているが、袖口に隠せるサイズの四面付与付きロッド、氷翅刃の魔剣については「立派な暗器である」と武具や対人戦闘の専門家であるヨナスは感心しているのだから。
いつの間に眠ってしまったのか。
まだ薄暗い時間だったが、腕の中の温かくて柔らかい体への未練を抱きつつベッドから出る。
勝手知ったる緑の塔。
シャワーを借りて、薄灰色のアンダーシャツに縫われた赤い花をひと撫でして身につける。
隊服は兵舎で着るが、ダリヤのニオイがうつったアンダーシャツを着て遠征に行くのが恋人を名乗る権利を得た己の新たな習慣だった。
それを聞いたダリヤが「私、そんなに臭う?」と泣きそうな顔で消臭剤を振りかけようとしたのを必死でとめた過去もあるのだが。
「おはよう……」
身支度を整えて寝室にいくとベッドはもぬけの殻で、それならとリビングに行けば半分ほど寝た状態のダリヤが緑の瞳をこすりながらコーヒーを淹れていた。
無理をさせた自覚のあるため、まだ寝ていたらどうかと思うのだが、ダリヤに『行ってらっしゃい』と言われたいので黙っていることにした。
・・・・・・
まだ眠い自分と、これから遠征に行くヴォルフのために濃いめに淹れたコーヒーをゆっくりひと口飲む。
夜を共にした翌朝、塔から王城にいくヴォルフに『行ってらっしゃい』という言葉をかけたらとても嬉しそうだったから、ヴォルフは寝ていてもいいというけれど見送ることに決めていた。
しかし、眠い。
遠征前夜はもう少し加減してもらえるよう申し出るか、体力増強を図るべきか。
上機嫌かつ妙なほど肌艶がよいヴォルフを見ながら真剣に悩んだが、朝悩むことではないと思って思考を切り替える。
「朝ごはんは?」
「王城で食べるよ、薬も飲まないといけないから」
化膿止めなどが入った微妙な味の薬を飲まなければいけないヴォルフに同情していると、
「それじゃあ、行ってくるね」
「いってらっしゃい……よい夢を」
自分は相当眠いらしい。
見送る挨拶がいろいろ混じってしまった。
「うん、ダリヤもよい夢を。絶対ここに帰ってくるから、帰ってきたら―――おかえり、と言って欲しい」
武勲も報奨も望まない、ただ声を聞きたい。
その声を聴くためなら、喜んで魔物の怨敵になろう。
そう誓い合うと同時に朝日が差し込み、金色と緑色の目が同時に光り輝いた。
END
スポンサードリンク
あとがき
「小説家になろう」で連載中の最新話(#401)で、ヴォルフが”怖い”と感じたのが印象的でつい妄想してしまいました。波乱の展開・・・ああ、早く更新していただけないかなぁ(*‘ω‘ *)


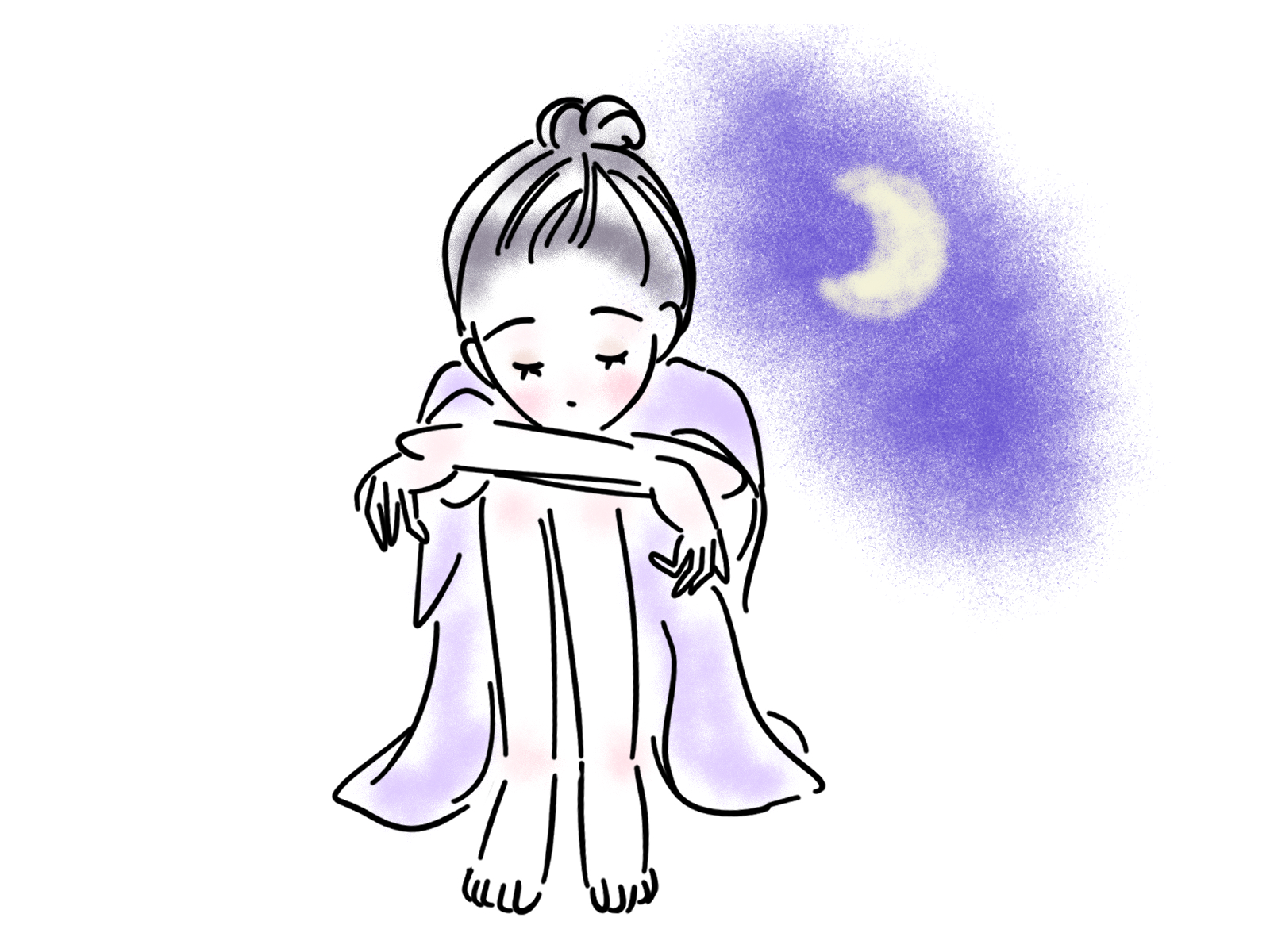
コメント