「魔導具師ダリヤはうつむかない」の二次小説で、ヴォルフとダリヤは恋人同士の設定です。
スカルファロット家に全力で応援されているヴォルダリ+「ヤキモチ」が書きたくて・・・友だちのときは妬かなくても、恋人になればヴォルフの過去が気になるかもしれないと妄想しました。
スポンサードリンク
視線を交わして、言葉をかわして、微笑みあう。
そんな『友達』の距離。
手を重ねて、首に腕を回して、相手の髪を指でかき分けて、唇を合わせて、素肌を触れ合わせて、無防備に漏れた吐息が耳に触れる。
そんな『恋人』の距離。
ヴォルフとの距離が恋人になって、新たに知ったヴォルフの一面はダリヤを甘く酔わせる。
「ダ…リヤッ」
すっかり溶かされたダリヤの脳がヴォルフの熱い声音に痺れる。
ふるりと体を震わせれば、自分を掻き抱く鍛え抜かれた太い腕に力が入り、少し苦しいくらいに強く抱きしめられる。
背が反り、鍛え抜かれた体に肺がつぶされて、絞り出た甲高い声が仄暗い闇に溶けていく。
脳には甘い霧がかかり、天井がみえるはずの視界はぼんやりとしていて。
力が入らず震える腕を持ち上げてヴォルフの広い背に触れると、そこは熱く汗に濡れていた。
――― この甘い熱を知る女が他にもいる
いつもならヴォルフに与えられた甘い熱の余韻を味わい、満たされた気持ちで意識を手放し眠りについた。
でもこの夜はダリヤの心にヴォルフの熱が届かない、冷たく固まった部分があった。
冷たい塊を飲み込んだのは数日前の夜。
その夜、ダリヤは男爵であり王城に出入りする商会の長として、苦手意識を抱えつつも参加した夜会でどうにか社交をこなしていた。
「初めまして」と挨拶されれば名前を覚え、「お久しぶりです」と再会の挨拶をされれば必死に記憶を探る。
その間も進む会話にオズヴァルドからの教えを思い出しながら、少し離れたところで自分のような焦りの欠片もなく社交を熟すイヴァーノを尊敬した。
社交場では男性よりも女性に対してのほうが気を遣うことに気づいたのはヴォルフの恋人になってから。
「王都随一の美男子」と言われるヴォルフの恋人であるダリヤを敵視する女性は多く、彼女たちはダリヤのミスを誘って無礼だと吊るしあげる気満々なのだ。
これについて、ダリヤは面倒だと思いつつも想定内ではあった。
なにしろ恋人未満のうちから軽く睨まれていたし、「どんなに突き刺さっても視線で死ぬことはない」とダリヤの女性たちに対する警戒は最低限だった。
だからなのだろう。
「初めまして、ロセッティ商会長。わたくしも一時期ヴォルフレート様とお付き合いしていましたの、どうぞお見知りおきを」
全く見知る気のない挨拶にびっくりするダリヤをさらに驚かせたのは、彼女が語るヴォルフとの一夜だった。
彼女はヴォルフの愛し方を知っていた。
ヴォルフと恋人になったのは最近でも友人として過ごす時間と密度はそれなりにあると思っていたため、この瞬間までダリヤは「過去に恋人はいなかった」というヴォルフの言葉を信じていた。
否、いまも信じている。
ただダリヤが気づかない振りをしていた。恋人はいなかったかもしれないが、女性とそういうお付き合いをしていたのかもしれないのだ。
なにしろダリヤと出会ったときのヴォルフはすでに立派な成人男性で、ダリヤと友だちになるにあたって「欲は娼館ではらす」と照れもせずにヴォルフは言い切ったのだ。
一夜の関係に慣れていたのかもしれない。
過去は過去だし、気にしても仕方がない。そう何度も言い聞かせても、”わたくしも”とそう言った女性、ダリヤも自分と一緒だといった女性の顔が忘れられなかった。
外見や声など、具体的なことを知りたくなかったというのが本音だった。
「ダリヤ?何かあった?」
ヴォルフの気遣う声が降ってくるが言えることではない。
心が氷を飲み込んだように冷たくて、温めて欲しくてヴォルフにしがみつく腕に力を込めれば、目の前の黄金色は一瞬驚いたものの直ぐに喜びで輝いた。
「ダリヤ」
甘く名前を呼ばれたあと、長い指が髪を優しくかきわけて、厚みのある手の平に左耳が覆われる。
それは彼女も知っていたヴォルフのキスの合図で、ダリヤの胸がチクリと痛んだ。
・・・・・・
「ヴォルフレート、貴方に確認したいことがあるのだけれどいいかしら?」
何となく定例になりつつある家族の食事会。
所用で領地から王都に来ていた前伯爵である父も参加した食事会は、グイードの娘であるグローリアのおしゃべりを中心に和やかに進んでいた。
そんな食事会が終わる間際、義姉であるローザリアの言葉にヴォルフは首を傾げつつも、断る理由、別邸の使い方うんぬんなど最近は後ろ暗いこともないので二つ返事で了承した。
「ありがとう。グローリア、お食事は終わったの?」
「はい。今日は疲れてしまったので、申しわけありませんがお先に失礼いたします」
グローリアがいてはいけない話なのか?
それにしても、穏やかではあるが自分に向けられる義姉の声音が気になる。
前回の定例会以後のことを高速で思い返す。特に別邸のことを中心に思い返したが訓練は大人しいものばかり、思い当たることは一切ない。
思わずヴォルフが助けを求めてグイードを見ると、兄はそっと視線をそらせた。
まるで生贄に捧げられたような心もとなさを感じていると、ローザリアが女性の名前をあげた。
貴族の勉強をしていたおかげで、その女性が子爵家の者かな程度の推察はできた。
「ご存知ですか?」
「家名は知っていますが、その女性は知りません」
なんとなく聞き覚えがある様な気がするが、ここで言うのは得策じゃないと感じて黙っていた。
「ヴォルフレートと同じ学院で、三度ほど同じクラスになったご令嬢よ。金色の髪に青色の瞳、お父上は財務部にお勤めです」
財務部と言われ、何かの用事で財務部にいったときにドレス姿の女性がいたことを思い出したが、そうだとしてもそれが何だというのだ。
「あなたの様子を見る限り問題なさそうですね」
「義姉上?」
「グイード様、お義父様、この件はわたくしにお任せくださいますね」
話はさっぱり見えなかったが、義姉のキレイな笑顔に兄以上の頼もしさを感じたヴォルフは黙っていることにした。
いつもの流れならば、このあとは父と兄との酒席になる。そこで訊ねればいい。
「ヴォルフ、私は妻を部屋まで送っていくから父上と先に飲んでいてくれ。今夜は少し冷えるし、そうだな、お前が以前持ってきてくれた柚子酒はどうだろう」
「いいですね。ダリヤに兄上が気に入ってくれたと言ったらもうひとつどうぞと、別邸にあるので今度もってきます」
「それは嬉しいね、もう残りが僅かだったから」
そんなに気に言ってくれたのかと嬉しい気持ちで兄を見れば、「父上がほとんど飲んでしまってね、隠しておいたのに」と教えてくれた。
「父上?」
「……グイードが美味いと言っていてな。お前も好きだと聞いていたし……ダリヤ嬢が作られたものなのだから、お前に許可をとるべきだったのだが……」
「どうでしたか?」
「美味かった。ヴァネッサは柑橘系を好まなかったから、そこは私に似たんだと……」
ポツリポツリと独り言のような父の言葉に、ヴォルフはダリヤから作り方を聞いて自分でも作ってみることを決めた。
「来年は父上にも贈ります」
「ああ、楽しみにしているよ」
そういってわずかに口元を緩めた父のあとをついて隣室に行くと、そこには柚子酒のお湯割りが二つ並んで湯気を立てていた。
ふと、父とこうして二人で飲み交わすのは初めてだと気づく。
「……こうして改めて向かい合うと緊張するものだな」
気まずそうな父の様子に、かつてウロスがレナートは口下手だと言ったことを思い出した。
以前大穴の話をしたときのように、今日も自分から話題を振ろう。
「あの、先ほどのご令嬢の話は何だったのでしょうか。父上はなにかご存知のようでしたが」
「少し前からお前と恋仲だったと噂されているご令嬢だ。本人が噂雀に歌わせている、枕を交わした深い仲だとな。毒にも薬にもならない話だからと放っておいたが、先日ダリヤ嬢に直接ケンカをふっかけた」
「な!?どうしてそれを教えてくれなかったのです!?」
今すぐにでも塔に行って誤解を解かなければと、腰を浮かしかけたヴォルフにレナートは苦笑する。
「花を害す虫はすぐに駆除される、すでに金色の梟がいろいろ突き始めたらしい。うちの花も動くということはそこかしこの夫人たちが何かするのだろう、貴族の既婚女性が出てきたら男たちは直ちに逃げなくてはいけない」
自分より背は高くなったが、まだ腕が短い末息子にレナートは貴族男子の心得を教えた。できれば「逃げの姿勢」ではなく、もう少し格好いい教えを説きたかったのが本音だったが。
「いま一度問うが、事実無根なんだな」
「はい。学院時代もその後もご令嬢と言われる方と枕を交わしたことはありません。ダリヤに会うまでは信用がおける娼館を利用していましたし、それだって馴染みを持たず適当に選んできましたから」
「ん?ん、うん……そうか」
反応の困る暴露をしてしまったと、父の反応をみて反省したヴォルフは勢いよく杯をあけ、手づからお代わりを作る。
そしてレナートにもお代わりがいるか訊ねると、
「やはりお前はヴァネッサの子だな、私はあまり酒には強くないのだが」
そう言って杯をあけた父親の目に光る負けず嫌いに思わず笑う。
そんなヴォルフにレナートは驚きながらも小さく笑い、その姿に控えていた者たちが目を潤ませたことを父子は気づかなかった。
・・・・・・
「さあ、ダリヤ。きちんと話をしておこうか」
昨夜は定例の食事会で家に泊ったヴォルフが朝早くに「ただいま」と塔に帰ってきたことにも驚いたが、出会い頭に抱きあげられてリビングのソファに運ばれてのこの状況にもっと驚いていた。
「家でいろいろ聞いた。どうして俺に相談してくれないのかとも思ったけれど、言いにくいことであることも理解した。それで結論だけど、そのご令嬢と寝たことはない。自慢じゃないけど過去に恋人がいたことはない、ダリヤが初めての恋人」
「うん、それは分かってる」
ダリヤとて彼女たちの妄言、恋人だったという言葉は信じていない。
だからそう言ったのだが、ホッとするヴォルフに少しだけ申しわけなくなったが、ここで聞かなかったら永遠に知り得ないかもしれないからと口を開く。
「それは分かっているんだけど……恋人ではなくても”一夜のお相手”ならあるかなって」
ヴォルフの体がピキッと固まったことに気づかないまま、やや火照った顔を俯けて続ける。
「以前そういうときは娼館に行くと言っていたから、学生のときだって……その、男性としての欲はあったでしょう?それで、相手も後腐れのない関係を受け入れていたなら……あり、かなって」
貴族の御令嬢については事実無根として反論もできるが、娼館の件は強く出られないヴォルフ。
ダリヤに対して「そういうときは娼館に行く」と言い切ったことについて、振り返って考察すれば自分の心に灯り始めた恋心を否定しようとしていた(のかもしれない)と言えるが、いまとなれば『言い訳』と取られても仕方がないわけで。
「どうしてダリヤの中で俺がその女性を抱いたことになるわけ?」
「だって、彼女はヴォルフの背中の古い……子どもの頃に負ったという傷跡のことを知っていたもの。それに……ヴォルフのクセを知っていたし」
「”クセ”?」
「”クセ”というのは変かも……技術、とか?」
「ちょ、ちょっと待って!クセって何?!技術?!」
ダリヤから出てきた言葉にギョッとし、そういう男だと思われていたショックと面白くない気持ちがヴォルフの中から吹っ飛んだ。
そんなヴォルフに対し、ダリヤは普段通り穏やかな表情で、話題が話題なだけに少しだけ羞恥に頬を染めながら続ける。
「だって、ヴォルフはいつも左腕で腰を、その、抱きしめてくるし。キスするときだって…いつも私の左耳をふさぐように右手を置くおくから」
「左腕で抱きしめるのは剣を右手で持つからだと思うけど……キスのしかたなんて意識したことがない。え、俺ってそうなの?」
「そうなの!耳を塞がれると自分の自分の声が籠って聞こえて恥ずかし……っ、んっ///」
二人の間にあった距離をヴォルフが一気に縮めると、反応できないうちに左耳を塞がれて口づけられる。
「ああ、本当だ。やりやすいのかな? 自分では何も意識してないけれど、確かに……他にもある?」
「……教えない」
「残念。 ああ、あと背中の古傷だっけ?」
顔を反らすと、ヴォルフに頬を突かれた。
「仕事柄けっこうケガするし、騎士団にそこそこ長くいるやつで背中に傷がない人なんてあまりいないよ?腕や足とは違って背中は再生できないから古い傷も結構残るし、そもそもいつできた傷かまでは言わなかっただろう?」
言われてみればそうだった。
「そもそも自分の背中なんて気にしないから……あ、ダリヤの背中はキレイだよ。肩甲骨の横に小さなほくろが一つあるくらい」
「え、そうなの?!」
今度は自分が驚かされた。
「あれ、肩甲骨じゃなくって腰の辺りだったっけかな?―――確認しないと、ね」
「えっと、ヴォルフ?」
夜の閨の雰囲気を醸し出したヴォルフからダリヤは後ずさったが、その長い左腕が伸びてきて腰をとらえられ、無骨な手が触れ、髪が指でとかされて左耳が覆われる。
ヴォルフが一歩距離をつめて、その黄金の瞳が欲しいと強請ってくるから、
「ここではイヤ」
そう言うと、腕を伸ばしてヴォルフの首の後ろで交差した。
それがダリヤのキスを受けいれるときのクセだと教えられたのは、数時間後のことだった。
END
スポンサードリンク
あとがき
「キスの仕方はクセのようなもの」と昔読んだ漫画にあったのを思い出してヴォルダリで再現してみました。
2020.8.31 スマホでも読みやすいように修正したのに併せて、過不足な表現を修正しました。

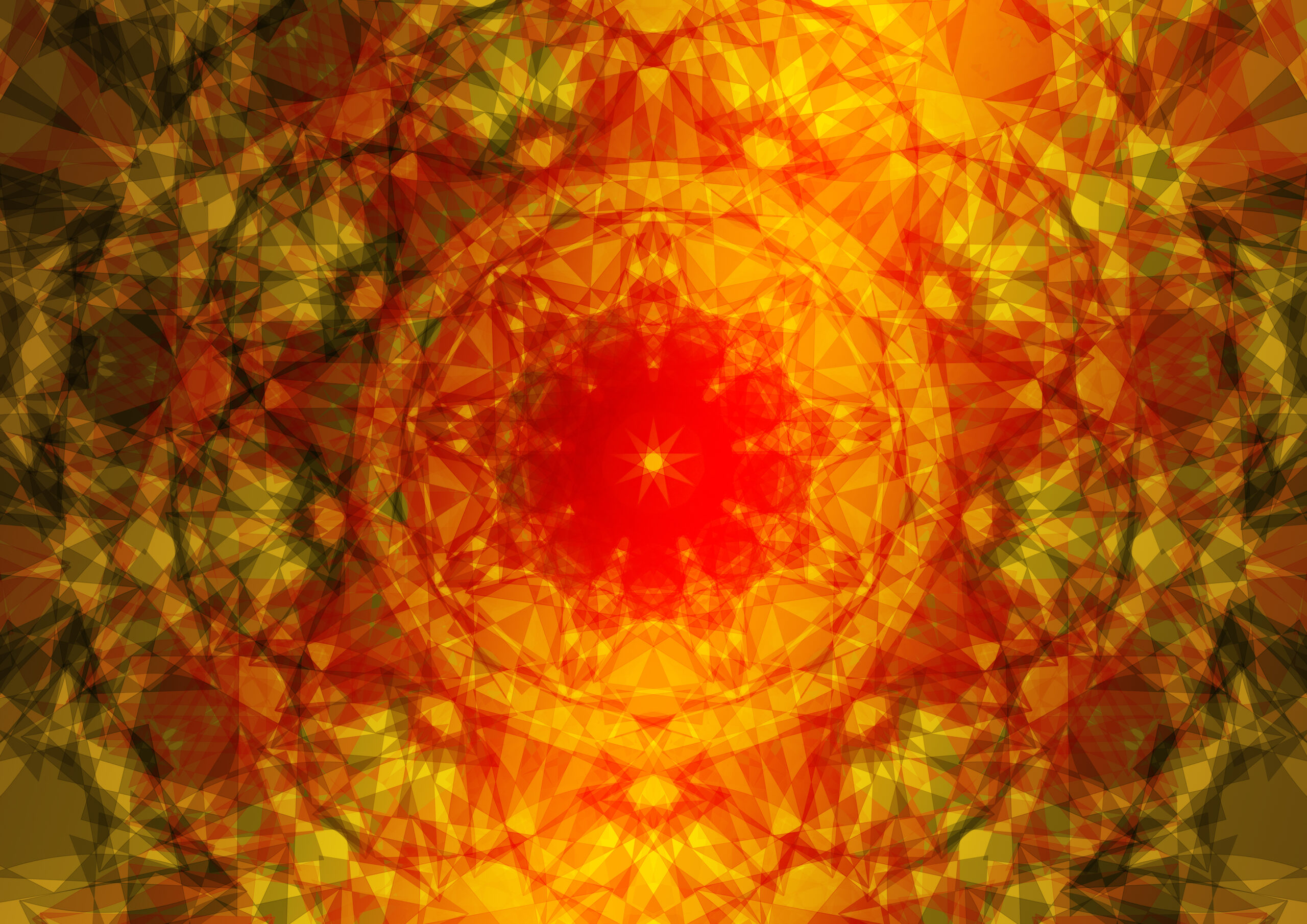

コメント