心霊探偵八雲の二次小説です(八雲視点)。
心霊探偵八雲が完結したため、今までアップした作品の設定を一部修正し、できるだけ原作「心霊探偵八雲 COMPLETE FILES」の書下ろし「それぞれの明日」のその後になるように修正しました。
本作は「完結後」ではなく、時系列では原作中、一心が亡くなった「その後」になります。
スポンサードリンク
叔父さんが死んで
僕は赤い瞳を隠すことをやめた
やはり隠していたことは何か枷になっていただろう。
コンタクトレンズを通さずに景色を見たとき、やけに心がスッキリしていた。
この左目と同じ紅い眼をもつ男。
それは僕の生物上の父親で、そして仇敵。
僕の大事な人たちの仇。
叔父さん
先生
あいつは俺の大事な人たちを殺した
目的は僕の精神を壊し、器を手に入れるため。
憎かった
憎くて 憎くて
殺してやりたかった
あいつと最後に対峙したとき、僕は拳を握り締めた。
大事なものをこれ以上奪われない様に、奪われ続けた過去の僕といまの僕は違うはずだったから。
スポンサードリンク
「やあっ!」
ノックも無く扉が開けば、元気な声とふわりと揺れる茶色の髪。
太陽のように明るい笑顔が、僕の中のどろっとした想いが霧散する。
彼女は僕のテリトリーにズカズカ入ってくる
トラブルや菓子
いろいろな物をもってきて
叔父さんが死んでから彼女はよくここに来る。
僕を元気づけるためだと推理しなくても分かるけど、ふとした瞬間に闇に心が囚われるときに現れるのは何故かは分からない。
普段は超がつくほど鈍いくせに、彼女は人の負の感情に敏感なのだろう。
「八雲君? わたしの顔に何かついてる?」
僕の視線の先で彼女が首を傾げるから
「目と鼻と口」
予想通り僕の答えが不満だったの彼女の白い頬が膨れる。
「失礼だなぁ」
「はいはい、悪かった」
別に君の顔を見ていたんじゃない、なんて言ったら彼女はもっと怒るだろう。
もしここで少し素直になって、「君の瞳を見てたんだ」なんて言ったら彼女はどんな反応を見せてくれるだろうか。
見てみたいけれど、照れ臭くて言えやしないんだ。
スポンサードリンク
「謝り方に誠意がなーい」
一通り喚くクセに、彼女の怒りは後を引かずにあっさりと治まる。
「新しいお菓子を買ってきたから、一緒に食べよう」
怒りの片りんもないニコニコ笑顔で僕の向かい側の椅子に座り、僕たちの間にある机に色とりどりの菓子が並ぶ。
イチゴの絵が目立つのはそういう」季節だからだろうが、イチゴの瑞々しい赤は僕の禍々しい紅色と違っ
パンッ
「いただきまーす」
心が黒くなりかけた瞬間になった音に僕はびくりとした。
そして心がすっと晴れたことに驚く。
彼女としてはただの習慣なのだろうが、まるで柏手のように効果てきめん。
「どうしたの? 食べてみてよ」
僕の前には薄い茶色の、明るい大きな瞳。
過去大勢から向けられた忌む眼とは違う、純粋に疑問だけを灯した瞳。
赤と黒の瞳を怖がること無くまっすぐと向けられる瞳。
ー キレイ ー
『あのとき』が簡単に蘇り、僕の口元が緩みそうになるから
「これを貰うよ」
特に選ばず、一番近いところにある菓子に手を伸ばす。
君がいなければ口にしない甘みがパッと広がる。
そして目の前でもパッと笑顔が咲く。
君は些細なことでも楽しそうに笑う。
君の笑顔を見ると心が温かくなる。
この優しい感情がアイツと僕の違い
アイツの遺伝を忌み嫌っていた僕は、気づけばアイツとの違いを必死に探している気がする。
君はその『違い』を僕にくれる。
だから『同じ』紅い眼を僕は、強く握った拳で何度もつぶそうと思った。
君がこの紅い眼をキレイだと言ったとき、長く握り続けた僕の拳がほどけた。
拳と一緒に僕の心の何かがするりと緩んだ
「うまい」
少しだけ素直になれば、僕の言葉で君が楽しそうに笑ってくれる。
君を笑わせられたのは僕だ。
その事実が僕の拳をまたひらく。
この拳が完全に開かれたら、僕は開いた手の平で明るい未来を掴めるのだろうか。
このさきも、僕は彼女といたいと思う
素直にそう言うことは出来ないけれど、君が傍にいてくれれば僕の未来は明るいだろう。
「そういえば、聞いてよ」
彼女との会話はなかなか面白い。
次は何を聞かせてくれるのか、少しだけわくわくする。
「今日ね、バスで痴漢にあったの!」
・・・ん?
スポンサードリンク
「その痴漢の人相は?」
大学の最寄りのバス停ひとつ手前で逃げたという不届き者の人相を問い、彼女の答えをメールにまとめて石井さんに送ることに決める。
「よくあるのか?」
「滅多にないよ」
滅多に…ゼロではないということだろう。
クマにパトロールさせるか?
「一発殴ってやればよかった」
興奮に振り回す彼女の小さな拳を受け止める
「君が殴ることは無い・・・僕が殴る」
「…本気?」
「もちろん」
「…八雲君ってこういう犯罪許せない性質だもんね」
君は大きな勘違いをしている。
君が被害者じゃなければ、痴漢探しなんて手のかかることは正直やりたくない。
僕はそこまで正義のヒーローは気取れない。
僕が拳を握って護りたいと思えるのは君ひとりだけだ。
「でも『殴る』なんて、八雲君らしくないね」
君のためなら拳を握るのも厭わないのだが、君は僕を完全には理解していない
「八雲君って喧嘩強いの?」
「さあね」
「何か頼りなぁい」
僕のお道化た回答に、彼女は本気にしないことにしたのだろう。
彼女はケラケラと楽しそうに笑った。
END



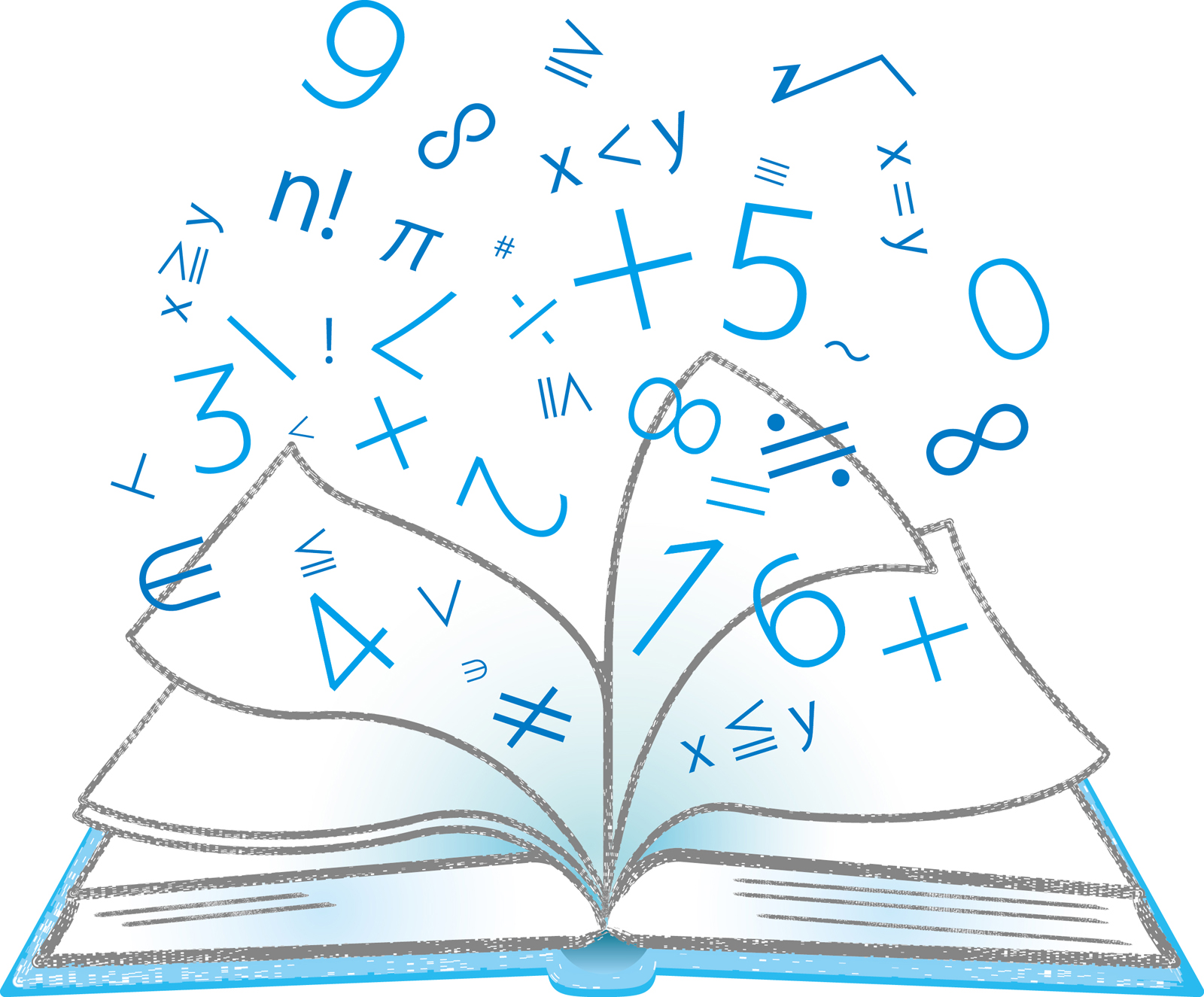
コメント