「名探偵コナン」の二次小説で、平次×和葉です。
平次と和葉は恋人関係で、少しだけ大人の表現があります(R指定には引っかからない程度)。ご注意ください。
スポンサードリンク
カラン コローン
洋館に合う重厚な鐘の音に新一は本から顔をあげる。
傍に置いてあるスマホに手を伸ばして画面を探るも、特に何の連絡もない。
首を傾げるつつも新一は読んでいたページにしおりを挟んで書斎から出た。
「やっぱり蘭か。 和葉ちゃんまで一緒なのは珍しいけど」
玄関に向かう前に外から開かれた扉。
カギをもっている人物で、鐘を慣らす人間は一人だけしかいない。
案の定、玄関ホールには新一の恋人である蘭がいた。
不思議なのは蘭と共に和葉がいることだった。
「あれ?何でいるの?事件は?」
「事件って今は特にないけど? 何だ、俺に会いに来たんじゃねえのか」
「留守と思ってきたのか」と、いささかふて腐れてた新一に蘭は手を合わせて謝る。
「新一と服部君は一緒だと思って。服部君を待つならうちより此処の方が和葉ちゃんも気が楽かなって」
「服部って…和葉ちゃん、何も聞いてねえの?」
心当たりなんて微塵もありません、という顔をした和葉に新一はため息を吐く。
和葉にわざわざ心配をかけたくなかったのだろうという平次の気持ちも分かるが、<この手のこと>を隠すのは得策とは思えなかった。
「俺、ちょうど腹が減っててさ。良ければ3人でポアロに行かねえか?」
自分が男女の機微に疎いことを新一は重々承知していた。
ここは人生の先輩に頼ることにして、空腹を理由に新一は2人をポアロに誘う。
可愛い笑顔で了承してくれた二人を玄関に残し、自室でこっそり電話を掛ける。
幸いカイシャにいたのか、2コールで出た相手に事情を説明すると
『新一君、俺はそんなにヒマじゃないんだが』
「ごめん、でも頼れるの降谷さん【しか】いなくて」
『君はいつからそんなにあざとく』
「でも、降谷さんも<こういうこと>に対する梓さんの意見を知っておきたくないですか?」
沈黙を了承ととった新一はにやりと笑った。
誰かそれを見ていれば、例えば一緒に幼児化した美女が見れば、江戸川コナンに似ていると評しただろう。
スポンサードリンク
「「「お見合い!?」」」
「服部君って未だ大学生よね?え、いまは大学生でもお見合いするの?合コンじゃないの?合コンなら結構経験あるわよ、私!」
(いや、梓さんの合コン経験談なんて怖くて聞きたくありません)
新一はカウンターに座って食事をする降谷を目だけ動かしてみる。
特に興味ない風にそこにいたが、『合コン』という言葉に端正な横顔がピクリと動いたのを新一の探偵の目は見逃さなかった。
新一としては『あはは~』と笑って誤魔化すしかなかった。
そのネタを掘り下げるつもりはなかったが、金髪のイケメンは違った。
「へえ~、梓さんは学生時代にかなり合コンに?」
「はい!大学時代には週一で行くこともありましたよ」
降谷の思わせぶりな振りは何も気づかない梓。
えへへ~っと若気の至りを披露する梓に新一の背筋には何十個もの氷が通り過ぎたが、
「将来自分でカフェを開きたくて。合コンだと格安で色々な料理を食べられるじゃないですか?」
「さすが梓さん!メニュー開発とは熱心ですね。そのときの努力がいま俺の胃袋をグッと掴んでいるということですね」
「これも美味しいですよ」とほほ笑む降谷。
「見合いといってもそんなに深刻になる必要はないですよ」
そして、取り戻した大人の余裕で降谷は青い顔をしている和葉に対して気遣う。
降谷は自分の容貌が女性受けが良いことを自覚していた。
仕事ではそれを十二分に活用するが、私生活では女性との距離感に悩まされていた(今は近過ぎても勘違いしない鈍感娘相手なので別の意味で悩み中)。そ
のため恋人以外脇目もふらない蘭と和葉は、降谷にとって付き合いやすい貴重な女性たちだった。
「彼のお父上が警察上層部の人間ですし、彼自身もいろいろ警察の事件に首を突っ込んでいるので今回の見合いを避けるのは難しいと判断したんでしょう」
「避けるのが難しいということは、お話をお受けするってことですか?」
「いいえ、直に会って相手から断ってもらうつもりなんですよ」
心配そうな顔をして和葉に寄り添う蘭に降谷は優しく微笑む。
そして二人に断りを入れてスマホをポチポチッと操作した。
「風見、ですよ」
そして探る目を向ける新一に答えを教える。
「彼なら直ぐにお見合い場所を突き止め、何かしらの手段を用いて情報を取ってきてくれるでしょう」
平然とパワハラかます降谷に新一は唖然としたが
「和葉さんにはお世話になってるからね」
「うち?うちなんて何もしてへんけど」
「服部君経由でとてもお世話になってるんですよ。んー、どうも和葉さんは自分を低く見る傾向があるようですね」
降谷の指摘に和葉は苦笑する。
「うちが平次にはつり合ってないのは分かるねん。平次はうちのこと好きやと言うてくれた。うちも平次のこと好きや。だけど【相応しくない】と言う子らの気持ちも分かるねん」
「そんなことない!」と口を揃える梓と蘭とは対照的に降谷はうなずく。
「確かに和葉さんの言う通り、服部君につり合う人や相応しい人は他にいるかもしれない」
「降谷さん!」と垂れ目をつり上げて怒る梓に降谷はにっこりと微笑んで、和葉に言い聞かすように優しく言葉を紡ぐ。
「でも服部君は和葉さんがいいという。それは服部君にとって和葉さんが【相性がいい】相手だからだ。相性ってのは理屈じゃないからね」
降谷の言っていることを理解した新一。
それとは対照的に、頭上に?を並べている女性陣に降谷は苦笑する。
「まあ、動物が番を求める本能みたいなものだから男の俺や新一君には分かりやすいんだけどね」
どう説明しようかと悩む降谷に、新一がその手の本能が目に見えて分かる赤井の名前を上げる。
「ほら、赤井さんの感じ、あれ、本能むき出しで宮野一筋、わき目も降らず宮野だけ溺愛してただろ?」
「志保さんはめっちゃ美人やん!スタイル抜群で大人の魅力ムンムン!めちゃくちゃ赤井さんとお似合いやん」
「あれは見た目の問題ではありませんよ。仮に志保さんが幼児のようだとしても…あいつは志保さんを求めましたよ」
「え!?降谷さん、ロリコンに理解があるんですか?」
「…はい?」
「もしかして降谷さんもロリコンとか?」
「…俺はJKもアウトです。JKに見えるくらいの童顔の成人女性なら話は別ですが」
「降谷さんも童顔ですもんねぇ、肩書きはゴツいですけど。…そういえば、降谷さんはお見合い経験ないんですか?」
「……まぁ、人並み程度にはありますよ」
ワクワクとしている梓に降谷はにーっこり笑う。
和葉の数%でも梓に不安がって欲しいと思いながら、新一はキュッと冷やされた肝をそっと撫でた。
「まあ、全て相手の方から断られていますからね」
「そう仕向けているとはいえ、よくそう毎回断わってもらえますね」
「そりゃあ色々手を尽くして。男色と言ってやろうと思ったこともあるよ」
「それはまた説得力がある…実は降谷さん…「それはないですよ、梓さん」」
3人のやり取りに置いてきぼりになっていた形の蘭と和葉だったが
「でも服部君が降谷さんみたいに上手にこなせるとは思えないんですけれど」
「だから風見に盗聴を指示したんです。和葉さん、あなたへの恩返しですよ」
スポンサードリンク
そんな東都のお話と、降谷の命を受けた風見がチャキチャキと仕事をこなした結果、2人ほどの工作員が今いるホテルの来たことを知らない平次の話。
平次は「若い2人で」と仲人の言葉を合図に部屋を追い出されたところだった。
去り際に母・静香の顔に浮かんでいたのは
『分かってるやろな。うちは和葉ちゃん以外は認めへんで』
それはもうブリザードも裸足で逃げそうな冷たい視線に思わず青ざめてしまったが、それは自分もやろうとしていたことで異論はなかった。
「平次さんとお見合いなんて夢のようやわ。うち、祖父の付き添いで府警にいき、そこで平次さんに初めてお会いして以来ずっとお慕いしていたんです」
「そうやったんか。大阪を基盤としているとはいえ、なぜあの代議士先生からお見合い話が飛び込んだか不思議やったん」
頬を染めて恋心を主張する彼女に平次は笑う。
「あの日以来、うちはずっと平次さんの活躍を追ってきました。大学に進学されて、あの工藤さんとご一緒するようになって一層華々しさが増したな思ってました。そして絶対に貴方のお嫁さんになると思ってたんです」
「…俺に恋人がいてもか?」
「もちろんです。貴方のような方に相応しいのは私。あんな子と貴方はつり合いません。どうしても情が残るというなら、愛人になさってはいかが?あんな子に貴方の妻はつとまりませんもの」
「愛人、ねえ」と平次は苦笑して頬を掻いた。
平次をよく知る新一や和葉なら、その目が一切笑っていないことに気づいただろう。
「【相応しい】とか【つり合う】とか、女は色々考えんなぁ。和葉もときどき言うねん。私は平次に相応しくないってな。 あんたを見たら和葉は俺に相応しいっちゅうんやろうなぁ 」
平次の言葉に彼女の顔つきが、その通りだというように自信に満ちるたが
「しっかし、あんたらの言う【服部平次】は全部遠山和葉って女が丹精こめて作ったもんやねん。なんてったって俺『褒められて伸びる子』やからな」
「…はい?」
「俺のやること為すこと、全部『すごいな~』って聞いてくれる和葉がいたから俺はここまで頑張ってきてん。あいつのキラッキラの目で褒められるの、俺、スゴイ好きやねん」
「でもそれは幼馴染だから…私だって貴方のことすごいと思っています」
「おおきに。でもやっぱり和葉に褒められるのとは違うわ。嬉しさが全然違う。あんたに褒められるくらいなら、その分も和葉に褒められたいなって思う」
「それは…慣れではないでしょうか」
「そうやろうな。あんたとも同じ時間を過ごせば、あいつに褒められたのと同じくらい嬉しくなるかもしれん」
「なら!」
「でも、その時間を全てあいつと過ごすのに使いたい。あいつにずっと褒められていたいねん、俺は。あいつに褒められると…そうやなぁ、俺の体中の細胞が喜ぶんや」
平次は自分の胸をポンポンッと叩いて微笑む。
「男の胃袋をつかむってよく言ったもんやな。細胞は1日に何億個も入れ替わる。俺のいまの体のほとんどはあいつの飯でできてるねん」
そういった平次がふっと笑うから、彼女は「どうしたんです?」と聞くと
「あいつ、いっつも何で俺がそんなに元気か聞くねん。あ、特にベッドでな。可愛い声で鳴いて、悦びながら堪忍堪忍って泣くんや。あの姿だけで何時間でも抱けるけどな。その体力をつけてんのはアイツの飯やねん。自業自得っていうのも変やけど、おもろい話やろ?」
彼女の美しい顔から自信が剥がれ落ち、唖然とした表情になったのを平次は内心で笑ってたたみかける。
「初めてあいつを抱いたとき、あいつときたら俺のこと初めてじゃないって言ったんや。その理由が上手いからやって。そんな意図はないんやろうけど、あいつはやっぱり俺を褒めてくれる。俺ももっと褒められたいからな、あいつがもっと気持ちよくなるように上手に抱きたくなるんや。つまり、俺に女の抱き方を教えたのもあいつやねん」
平次はケタケタと笑って
「あんたは和葉を愛人にしても良いというが、お前にとって【旦那】って何やねん。おとんに圧力かけて俺を無理矢理あんたの旦那にしても、俺は俺の時間を全て和葉に使う。俺が抱きたいのもあいつだけやからな、俺の子を産むのも和葉やろう。なあ……一体【旦那】って何やろなぁ」
「…私は何をすれば……」
「知らん、そんなの俺にも分からん。自分でも訳が分からんくらい、俺にはあいつだけやねん。見合いのことは好きにしたらええ、もともと服部の家には選択肢がない見合いやからな」
「それじゃあ俺は東京、和葉のところに帰る」というと、平次は呆然とする彼女を置いて美しい日本庭園から直接ホテルを出ていった。
スポンサードリンク
「ただいまぁ、何で連絡したんに俺の部屋におらん…って、何してるんや?」
「へ…平次ぃ///!?」
勝手知ったる我が家で合い鍵を使って和葉の部屋に入ってきた平次は、スマホを持ったまま真っ赤な顔をした和葉に出迎えられた。
和葉の握るスマホから微かに漏れ聞こえるのは男の声で
「…誰と電話してんねん、ちょい貸せや!」
まさに恋する乙女を象徴するような顔の和葉からスマホを奪い取った平次。
聴こえてくる音声に耳にすると、浅黒い顔がみるみる間に真っ赤になって
「何でこんなん……工藤! いや、公安の連中の仕業やな!!こんなやつすぐ消せ!聞くなや!!」
「…無理や。もう何十回も聞いてもうた………平次ぃ」
泣き笑いして抱きついてくる和葉を抱き留めて、寄ってきた桃色の唇を最後に目を閉じて…
(俺、一生和葉に敵わんやんけ///)


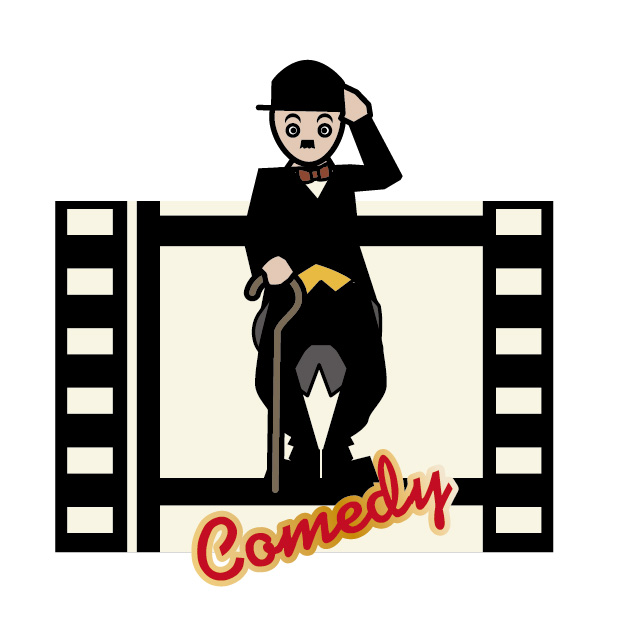

コメント